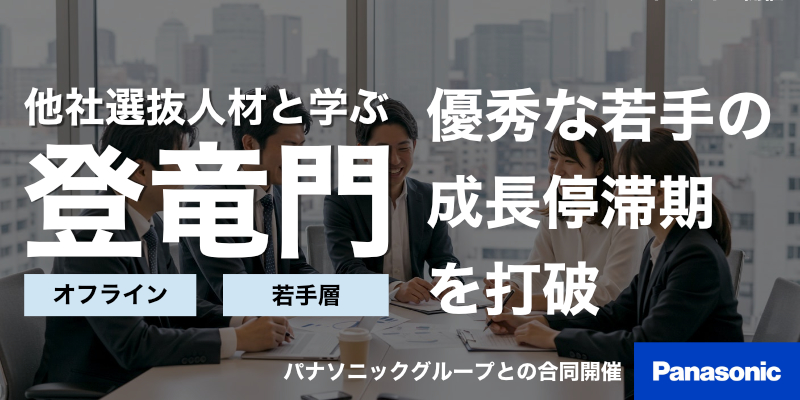ハイプレッシャーな環境下で、自分の限界を突破する感覚をつかめる研修だと思います。

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社
上席執行役員
社長室長兼People Experienceデザイン本部長
西田 宏 様
ー 現在の担当業務について教えてください。

当社グループは、もともとはCCCの子会社で主にTSUTAYAにコンテンツを供給する役割を担っていました。2022年にMBOしてCCCから独立し、現在は映像・音楽・出版/メディア・グッズ販売など、幅広いエンタテインメント事業を展開しています。グループ全体では約20社・計900名が在籍しており、日々多彩なコンテンツを世の中に届けています。私は社長室長として、グループの企業間連携を強化する“横串”の役割を担っていますが、昨年度から「People Experienceデザイン本部」も兼任することになり、人事・総務・ITなどを通じてグループで働く人々にとっての体験価値向上も目指しています。現在は約30名のメンバーとともに、グループ全体の基盤づくりに取り組んでいます。
ー 「登竜門」を採用した経緯、背景を教えてください。
Indigo Blueさんには、当社の人事制度の改訂・構築でもご協力いただいており、そのご縁で「登竜門」という新しい研修プログラムについてもご紹介いただきました。若手の次期幹部候補を対象に、他社と合同で行う研修という点に非常に興味を持ちました。当社では「LEAF」という次世代リーダー育成プログラムを立ち上げており、月1回程度の講演会や勉強会を開催しています。その参加メンバーの中に、「登竜門」にぜひ参加させたいと思える人材がいたため、試験的に1名を派遣することにしました。
ー 「登竜門」で、御社の受講者は活躍されていたと伺いました。
おかげさまで、当社の受講者は研修中かなり頑張っていたようです。彼は「課題を解決するタイプ」というより、「問題を見つけて課題化するタイプ」だったかもしれません。登竜門には大企業の優秀な方々が多く参加されていて、当社の受講者は少し異色だったかもしれません。どちらかというと“クセが強い”タイプで、いわゆる優等生タイプではありません。でも、そうした個性が逆に目立って、良い方向に働いたのではないかと思います。彼は現在、クリエイター陣をまとめるような業務を担当しており、日頃から現場の多様な価値観と向き合っています。そうした経験が、今回の研修の場でも独自のアプローチや人との関わり方に活かされたのかもしれません。
ー 「登竜門」の研修形式について、効果的だった点は何だと思いますか?
やはり、人はプレッシャーの中で仕事をしたり、修羅場を経験したりすることで成長するものだと思います。そうした状況を通じて、人材としてのキャパシティが広がっていくのではないでしょうか。風船を膨らませるとき、ある程度パンパンになった状態から、さらに空気を送り込まないともっと大きな風船にはなりません。でも、それには破裂のリスクを伴います。これは人材育成にも通じる話です。キャパオーバーに近い状況でさらに仕事をこなすことで、容量が広がっていく。ただし、人材を“破裂”させるわけにはいきません。だからこそ、登竜門のような研修の場で、ハイプレッシャーな環境に身を置き、自分の限界を突破する感覚をつかむことができれば、それは非常に貴重な経験になると思います。
ー 風船の例え、とても面白いです。
コンプライアンスや働き方改革といった時代の流れもあり、パンパンになりかけている風船(人材)に対してもう1プッシュ、2プッシュ空気を入れることは難しくなっています。マネジメント側も部下が無理をしていないか気にしますし、本人も断ることができる、また断るべき世の中に変わってきていると思います。我々の時代は、周囲から空気を入れられて膨らむことで育ってきましたが、今はそのあり方が変わってきています。
ー ご自身の成長に繋がったと思う修羅場の経験にはどのようなものがありましたか?
ふたつあります。ひとつは、20年くらい前になりますがカルチュア・エンタテイメントグループ設立以前、CCCの社長室長を務めていた4年間です。社長の時間のクオリティをいかに高められるか、それが自分が果たすべき役割だと決めて日々戦っていました。具体的なエピソードというより、毎日あらゆることを考え、行動し、判断する連続でしたので、それを4年間続けたことで自分のキャパシティが大きく広がったと感じています。もうひとつは、同じくCCC時代の話ですが、買収した子会社の社長を任されたことです。赤字で資金繰りに苦しむ会社でしたが、コスト削減などを進め、最終的には黒字化することができました。経営者の責任とは何かを身をもって経験できた貴重な時間でした。

ー 今後もIndigo Blueの研修を受講するご予定はありますか?
今後も、自己成長に対して貪欲な人材をIndigo Blueさんの研修に送り出していきたいと考えています。最終的に人が成長できるかどうかは本人の意志次第ですが、Indigo Blueさんの研修では、普段あまり使わない脳を刺激するような体験も含め、それを楽しみながら取り組むことができます。研修を通じて何かを得て、それを自分の力に変えたいという意欲的な人材にとっては、非常に有意義な機会になると思っていますので、会社としてもそうした人材の成長を支援していきたいと考えています。
ー 今後の人材育成の目標や構想がありましたらお教えください。
ひとつは、管理職のレベルアップです。管理職には、法令に則った管理監督者としての責務に加え、アウトプットを最大化するリーダーとしての役割も求められています。管理職者たちがそうした期待に応えられるよう、スキルアップや能力開発の機会を体系的に整備して、支援する体制を整えていきたいと考えています。もうひとつは、現場社員の育成です。当社はエンタテインメント業界で、コンテンツを創り出し、世に発信する仕事をしています。ですので、自分の「好き」を仕事にしている社員が多いのですが、「好き」だけでは商売として継続できません。だからこそ、自分の「好き」という想いをビジネスとしても成立させられる人材に育てていくことが、今後の大きなテーマだと思っています。